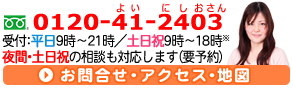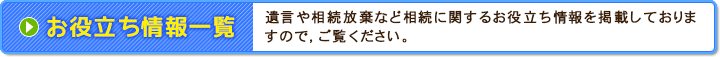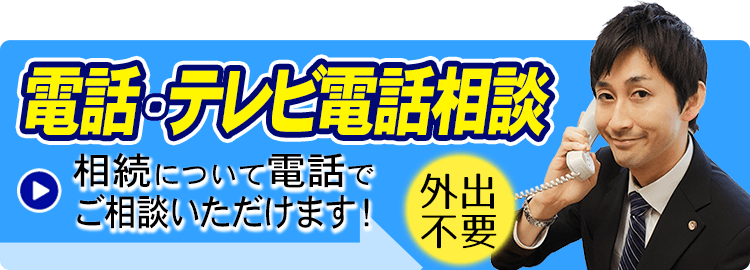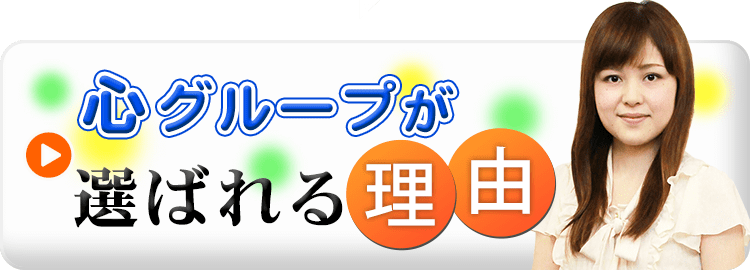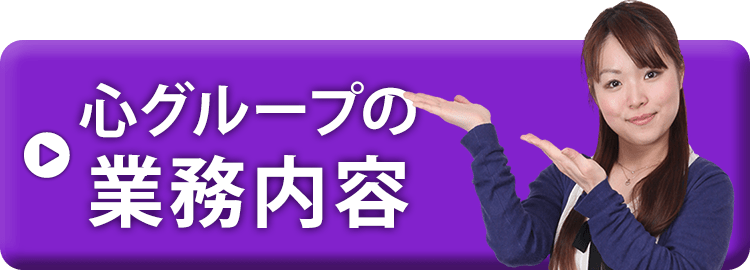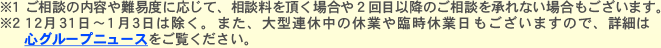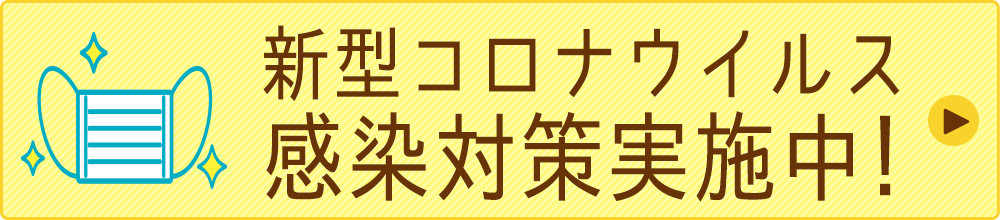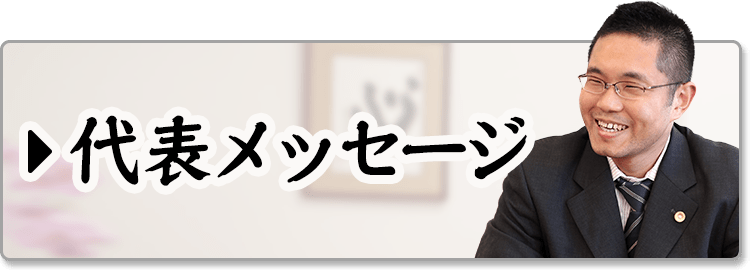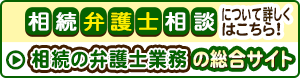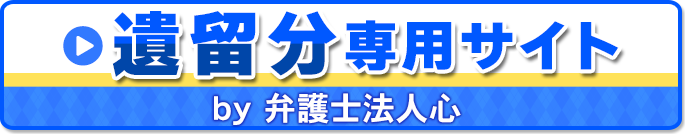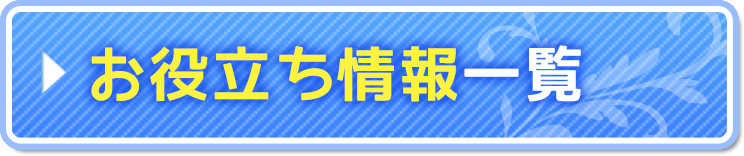寄与分に関するQ&A
寄与分が認められる要件は何ですか?
寄与分の要件は次のとおりです
① 相続人自らの寄与があること
寄与分が認められるのは、原則、相続人だけです。
そのため、例えば、親の面倒を相続人である長男ではなく、その配偶者が見た場合、長男の相続分を増やすことにはなりません。
もっとも、例外的に相続人の配偶者の寄与分が認められたケースもあります。
また、特別寄与料の支払請求は、相続人でなくとも一定の範囲の親族であれば認められます。
② 「特別の寄与」であること
介護や家事の手伝いなど、亡くなった方への貢献が全て寄与分として認められるわけではありません。
例えば、子供は親に対して扶養義務を負うため、簡単な介護は子供の義務として行うべきものであって「特別」ではなく、相続の取り分では考慮されなくなります。
何をもって「特別」とするかの判断は難しいのですが、「被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献」にあたるとされています。
つまり、「親子であれば親の面倒は少し大変でも見るべき」という考え方であれば、子が親の簡単な介護をしただけでは、通常子供として期待される程度の貢献として「特別の寄与」ではないとの判断がされやすくなります。
一方で、相続では、甥や姪が相続人となることも珍しくありません。
世間一般の感覚として、甥や姪が同居をして付きっきりで叔父の介護をすることは珍しいと思います。
そのため、子供であれば同居をして付きっきりで介護をしても「特別な寄与」とは言われないケースもありますが、甥や姪が同じように付きっきりで介護をすれば、寄与分は認められやすくなります。
③ 遺産が維持又は増加したこと
相続人の行為により、被相続人が支払うべきだったものを支払わなくて済んだこと、もしくは被相続人の財産が増加したことが必要になります。
例えば、相続人が介護したことによって、亡くなった方が生前に老人ホームに入所しないで済んだというケースです。
この場合、本来老人ホームに支払うべきだった入所費用を支払わなくて済んだおかげで、相続時に預金が残っていたということで、寄与分が認められる可能性があります。
また、相続人が親のために家を買ってあげた場合、相続ではその家も相続人全員で分けることにはなりますが、家を買ってあげた相続人は寄与分として相続の取り分を増やすことができるケースもあります。
④ 寄与行為と遺産の維持又は増加に因果関係があること
「親の面倒を見る」というと、様々なものが考えられますが、寄与分として認められるためには、相続人の行為により財産が増えていなければなりません。
しかし、相続人の行為により財産が増えたことの因果関係を示すことが難しい場合もあります。
例えば、独りで住む親のもとを頻繁に訪れ、その話し相手となってあげることは重要なことです。
人と話すことで認知症の進行を防ぐことができ、老人ホームに入らなくてもよくなるかもしれません。
しかし、そのような形に残りづらい精神的なサポートは、直接お金に換算しにくいものであるため、因果関係が無いとして寄与分が無いとされるケースもあります。
相続人ではない親族は寄与分の請求ができないのですか?
以前は、寄与分の主張は相続人でなければできませんでした。
しかし相続法改正により、特別寄与料の制度が創設され、相続人ではない親族も寄与分の請求ができるようになりました。
例えば、子供が自立して家を出てしまい、近くに住んでいた兄弟やその子供(甥姪)が一人暮らしの方の面倒を見ているというケースはよくあります。
この場合、相続人はあくまで家を出た子供となるため、兄弟やその子供は寄与分の主張ができませんでしたが、相続法改正後は、このような相続人ではない親族も寄与分の請求ができるようになりました。
なぜ特別寄与という制度が創設されたのですか?
亡くなった方のお世話をしていた方の利益を図るためです。
今までは、相続人ではない親族が、寝たきりの方をずっと介護していたようなケースであっても、相続人でないというだけで何の権利も認められませんでした。
そういった不公平を是正するために、新しい制度が創設されました。
自筆証書遺言の書き方に関するQ&A 遺留分と生前贈与に関するQ&A